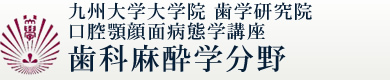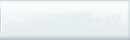主な研究テーマ
1.周術期糖代謝管理についての研究
術後感染や悪性腫瘍の術後再発は、外科医の技術によって抑え抑えることはできません。周術期の高血糖によって予後が不良になること、手術中の血圧低下や輸血などによって有意に腫瘍の再発率が増加することは20年以上前から知られています。しかし、適切な手術中の麻酔管理についてはあまり検討されていませんでした。当教室では人工膵臓を用いた周術期糖代謝管理による予後の改善についての検討を進めています。
2.歯科診療中の危機的偶発症の予防と救命処置についての研究
近年、Basic Life Supportのような一次救命処置が導入されています。しかし、これらは日常生活において発症する危機的状況に対する救命処置です。歯科診療はデンタルチェアの上で行われます。速やかに床に移動できない場合も多いため、心肺蘇生や気道閉塞の解除はデンタルチェア上で有効に行われなければなりません。歯科医院における危機的偶発症を減少させ、発生した危機的偶発症に対する具体的な救命処置の方法とその効率について検討しています。
「ヨーロッパの蘇生ガイドライン2021で、横山教授の考案した丸椅子の使用を推奨」
当科では、歯科診療中に発症する重症偶発症への対策が重要だと考え「歯科治療中の心停止では、そのままデンタルチェア上で心肺蘇生を行う」ことと、「丸椅子で安定させて胸骨圧迫を行う」ことを提唱しています。
今回改訂されたヨーロッパの蘇生ガイドライン2021(European Resuscitation council Guidelines for Resuscitation 2021)では、この2項目が、一杉講師、横山教授の文献を引用して推奨されています。
歯科治療中にデンタルチェア上の患者が心肺停止になった場合には、床に下ろさずに心肺蘇生を開始し、背板の下に丸椅子をおいて安定させて胸骨圧迫を行いましょう。
研究に関するお知らせ
1. 齲歯治療のための全身麻酔前の血液検査結果を活用した小児の臨床参考範囲設定の検討
1.臨床研究について
九州大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、臨床研究を行っております。当院歯科麻酔科・九州大学大学院歯学研究院では齲歯治療を中心に歯科処置や手術のため全身麻酔を行った小児の患者様の術前検査の血液検査の結果について臨床研究を行っています。
2.研究の目的や意義について
小児では、自覚症状が明瞭でないことから、客観的に判断できる検査値から得られる情報は非常に重要です。血液検査の結果を正しく評価するためには正常化異常かを判断するための基準範囲が設定されていなければなりません。しかし、小児では採血量や採血行為の負担、倫理面での問題があり、健常者の検体を得ることが極めて困難です。さらに年齢区分と性別が重要であり、新生児、乳児、幼児、学童、青年期に分けて考える必要があります。しかし、各年齢層にわたり健康なボランティアを得にくい上、発育度の個体差が大きいので分布のバラツキが大きいといった問題があります。さらに病院を受診される患者様の血液検査結果には異常値が含まれることが多いため、小児の基準範囲を設定することは、非常に困難な状態です。
今回の研究では、小児の基準範囲の設定における対象を、齲歯治療を中心として歯科での手術や処置に対する全身麻酔を受ける患者を母集団とします。なぜなら当診療科において全身麻酔を行う患児は、合併症や内服歴のない児が多く、血液検査で異常値を示す症例を排除できる可能性が高いからです。また、全身麻酔前には、身体異常がない状態でスクリーニング目的に血液検査を行っており、同一検体で32の生化学・血液検査項目を活用することができます。
今回の研究により、現在の検査法に則した、より臨床的に適正な基準範囲を調査します。
3.研究の対象者について
2009年4月1日から2021年12月31日までに九州大学病院歯科麻酔科で全身麻酔のための術前検査を行った約2000症例の患者様の血液検査結果を対象とします。
4.研究の方法について
この研究はカルテより血液検査に影響するような全身疾患や内服がない患者様の血液検査結果を取得し、統計的な手法を用いて実施します。
5.個人情報の取り扱いについて
研究対象者のカルテ情報をこの研究に使用する際には、容易に研究対象者が特定できる情報を削除して取り扱います。
2. 急速導入時の盲目的経鼻挿管の成功率と術後合併症の検討
1.臨床研究について
九州大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究し、診断法、治療法の改善に努めています。その一つとして、九州大学病院歯科麻酔科では、現在全身麻酔で経鼻気管挿管を受ける患者さんを対象として、盲目的気管挿管に関する「臨床研究」を行っています。
今回の研究の実施にあたっては、九州大学医系地区部局観察研究倫理審査委員会の審査を経て、研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は承認許可日から2027年3月31日までです。
2.研究の目的や意義について
全身麻酔の際には気管挿管の気管チューブを通して人工呼吸されます。気管挿管を実施するには、十分な麻酔薬を投与されて意識がない状態で「喉頭展開」という操作が必要です。この操作によって声門を直視して気管内に気管チューブを進めます。喉頭展開は喉頭鏡という器具を用いて、喉頭の手前にある喉頭蓋を持ち上げるようにして声門が見えるようにする操作です。そのため、患者さんは意識消失していますが、その刺激でストレスホルモンが誘導され血圧が上昇して脈も早くなります。
経鼻挿管は鼻腔を通して気管チューブを気管内に進める挿管方法です。最初に鼻孔から咽頭まで気管チューブを進めておき、喉頭展開してさらに気管チューブを気管内に進めます。この方法は百年ほど前に確立されていて、当時から盲目的に気管挿管するということも行われていました。われわれも麻酔導入に際して、喉頭展開なしに、手指の感覚によって盲目的に経鼻挿管するという手技を確立しています。また、成功率がある程度高く、呼吸器合併症が少ないということも経験的に知っています。
そこで、今回歯科麻酔科では、盲目的経鼻挿管の成功率や麻酔後の呼吸器合併症の発症リスクを検証することを目的として、本研究を計画しました。本研究を行うことで、患者さんが喉頭展開という侵襲的な操作を受けることなく、また術後の呼吸器合併症も少なくなれば周術期管理に有益です。
3.研究の対象者について
九州大学病院歯科麻酔科では内視鏡下を用いたファイバー挿管や、特殊な挿管についてはビデオで記録を残しております。今回は2025年4月1日から研究許可日前日までに九州大学病院中央手術室で全身麻酔を受けられた方の内、教育目的に盲目的気管挿管の操作のビデオ記録がある患者さん100名を対象にします。
研究の対象者となることを希望されない方又は研究対象者のご家族等の代理人の方は、事務局までご連絡ください。
4.研究の方法について
この研究を行う際は、カルテとビデオ記録より以下の情報を取得します。また、保管されている麻酔記録を用いて、盲目的経鼻挿管の成功率と所要時間を算出します。取得した情報の関係性を分析し、術後の咽頭痛および嗄声リスクを明らかにします。
〔取得する情報〕
年齢、性別、身長、体重、マランパティー分類、ASA-PS(全身状態の評価)、盲目的気管挿管の成否、
挿管に要した時間、術後の咽頭痛の有無と程度、嗄声の有無と程度
〔利用又は提供を開始する予定日〕
研究許可日以降
5.研究への参加を希望されない場合
この研究への参加を希望されない方は、下記の相談窓口にご連絡ください。
なお、研究への参加を希望されなくても、あなたに不利益になることは全くありません。
その場合は、収集された情報などは廃棄され、取得した情報もそれ以降はこの研究目的で用いられることはありません。ただし、すでに研究結果が論文などで公表されていた場合には、完全に廃棄できないことがあります。
6.個人情報の取扱いについて
研究対象者のビデオ記録、測定結果、カルテの情報をこの研究に使用する際には、研究対象者のお名前の代わりに研究用の番号を付けて取り扱います。研究対象者と研究用の番号を結びつける対応表のファイルにはパスワードを設定し、九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野内のインターネットに接続されていないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、同分野の職員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。
また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、研究対象者が特定できる情報を使用することはありません。
この研究によって取得した情報は、九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野・教授・横山武志の責任の下、厳重な管理を行います。
ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希望される方は、ご連絡ください。
7.試料や情報の保管等について
〔情報について〕
この研究において得られた研究対象者のカルテの情報等は原則としてこの研究のために使用し、研究終了後は、九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野において同分野教授・横山武志の責任の下、10年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。
しかしながら、この研究で得られた研究対象者の情報は、将来計画・実施される別の医学研究にとっても大変貴重なものとなる可能性があります。そこで、前述の期間を超えて保管し、将来新たに計画・実施される医学研究にも使用させていただきたいと考えています。その研究を行う場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、承認された後に行います。
8.この研究の費用について
この研究に関する必要な費用は、部局等運営経費でまかなわれます。
9.利益相反について
九州大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進しています。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれることもあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、国や大学も健全な産学連携を推奨しています。
一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反(利益相反)しているのではないかという疑問が生じる事があります。そのような問題に対して九州大学では「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医系地区部局における臨床研究に係る利益相反マネジメント要項」を定めています。本研究はこれらの要項に基づいて実施されます。
本研究に関する必要な経費は部局運営経費でまかなわれており、研究遂行にあたって特別な利益相反状態にはありません。
利益相反についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の窓口へお問い合わせください。
利益相反マネジメント委員会
(窓口:九州大学病院ARO次世代医療センター 電話:092-642-5082)
10.研究に関する情報の公開について
この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことができます。資料の閲覧を希望される方は、ご連絡ください。
この研究に関する情報や研究成果等は、以下のホームページで公開します。
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野ホームページ
: https://www.dent-anesth.dent.kyushu-u.ac.jp
また、この研究では、学会等への発表や論文の投稿により、研究成果の公表を行う予定です。
11.特許権等について
この研究の結果として、特許権等が生じる可能性がありますが、その権利は九州大学及び共同研究機関等に属し、あなたには属しません。また、その特許権等を元にして経済的利益が生じる可能性がありますが、これについてもあなたに権利はありません。
12.研究を中止する場合について
研究責任者の判断により、研究を中止しなければならない何らかの事情が発生した場合には、この研究を中止する場合があります。なお、研究中止後もこの研究に関するお問い合わせ等には誠意をもって対応します。
13.研究の実施体制について
この研究は以下の体制で実施します。
| 研究実施場所 | 九州大学病院歯科麻酔科 九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野 |
|---|---|
| 研究責任者 | 九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野 助教 大島優 |
| 研究分担者 |
九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野 教授 横山武志 九州大学大学院歯学府歯科麻酔学分野 大学院生 河野桃子 九州大学病院歯科麻酔科 医員 西村怜 |
14.相談窓口について
この研究に関してご質問や相談等ある場合は、下記担当者までご連絡ください。
| 事務局 (相談窓口) |
担当者 :九州大学大学院歯学研究院歯科麻酔学分野 助教 大島優 連絡先 :〔TEL〕092-642-6480(内線6480) 〔FAX〕092-642-6480 メールアドレス:oshima.yu.278@m.kyushu-u.ac.jp |
|---|
【留意事項】
本研究は九州大学医系地区部局観察研究倫理審査委員会において審査・承認後、以下の研究機関の長(試料・情報の管理について責任を有する者)の許可のもと、実施するものです。
九州大学病院長 中村 雅史